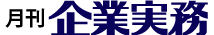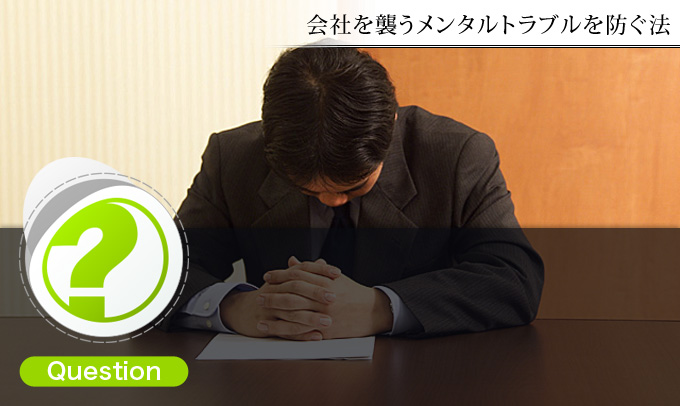
メンタルヘルスの不調により、遅刻・欠勤が続いている従業員がいます。当社の就業規則には「精神又は身体の故障により業務に堪えられないときは解雇できる」とあり、直ちに本人を解雇しようと思いますが、問題ないでしょうか?

法律上、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には無効となります。メンタル不調により勤務困難となった従業員を直ちに解雇することは、「社会通念上相当」と認められず、無効となる可能性が高いので、問題があります。
従業員を「解雇する権利」には法律上強い制約がある
解雇については、労働契約法という法律で、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており(労働契約法16条)、法律上強い制約があります。
端的にいえば、
- 就業規則で解雇原因が定められており、従業員がその原因に当てはまる(客観的に合理的な理由がある)場合で、
- 原因の程度が重大で解雇以外の手段が考えられず、従業員側に酌むべき事情がほとんどない(社会通念上相当である)場合
でなければ、解雇は無効となります。
本事例のように、精神または身体の故障により業務に堪えられない従業員を解雇できることは、多くの会社の就業規則で定められています。
しかし、実際に従業員が業務に堪えられないとしても、解雇以外の手段をとり得るならば「社会通念上相当である」とは認められず、解雇は無効となります。
とはいえ、遅刻や欠勤が続く社員をそのまま放置しておくことは、労務管理の点からみても問題です。以下、メンタルヘルス不調者への対応について説明いたします。
トラブルを防ぐメンタル不調者への対応手順
Step(1) 症状の把握
社内でメンタルヘルスの不調を訴える従業員がいた場合、まずは症状を正確に把握する必要があります。
本人との面談は必須ですし、仮に本人が主治医の作成した診断書を持参したとしても、別に会社の指定する医師の診察を受けてもらうことも有効です(受診命令の可否については、メンタル不調が心配される部下に「病院へ行け」と命令することはできる?を参照)。
Step(2) 措置の検討
症状を把握したら、次にどのような措置が適切か検討します。
実際にはケースによって様々な措置が考えられますが、代表的なものとしては、軽い順に、次の3つが考えられます。
①勤務時間の短縮
②配置換え
③休職命令
①勤務時間の短縮と②配置換えは、現在よりも仕事の負担を軽くすることですが、両方まとめて行うことも考えられます。
③休職命令は、①勤務時間の短縮と②配置換えよりも重い措置であるため、これらが不可能である場合に初めて検討すべきです。
Step(3) 休職命令
休職命令とは、従業員が求められる労務の提供ができない場合に、会社の一方的な命令によって従業員を一定期間休ませることを指します。休職期間中は給料を支払う必要がありません。
休職期間中に治癒すれば復職となりますが、治癒せずに休職期間が満了した場合には自然退職(雇用契約の自動的な終了)となる旨が就業規則で定められていることがほとんどでしょう。
解雇となると予告手当の支払等の手続きが必要になり、会社の負担が増えるからです。
休職命令は、退職につながりうる重い命令のため、通常、どのような場合にどのくらいの期間を命令できるか就業規則で定められています。
また、休職命令を出すための条件(労務の提供ができないこと)の判断は微妙なため、代替として、給料を支払った上で一定期間出勤しないように命じる「自宅待機命令」を出すこともあります。
Step⑷ 休職期間満了時の措置
休職期間満了時点で、治癒したかどうか、また、治癒していないとしてもどのような症状なのかを把握するために、従業員本人に医師の診断書を提出させ、場合によっては会社が指定する医師の診察を受けさせる必要があります。
診断書の費用負担を含め、診断書の提出義務と会社指定医による受診義務については、就業規則で定めておきましょう。
診断の結果、休職前の業務には復帰できなくともより軽い業務に就くことができ、従業員本人が軽い業務を希望する場合には、会社は可能な限り軽い業務に就かせる義務があります。
また、本人が軽い業務を希望しない場合でも、ほどなく回復して休職前の業務に就くことができると見込まれるならば、本人の職種が限定されていても、可能な限り軽い業務に就かせる義務があります。
こうした義務を尽くしても復職させることができず、かつ本人から退職願が出ない場合に初めて、解雇を検討します。
解雇については、最初に述べたとおり、法律上強い制約があり、最終的には個々のケースに応じた高度な専門的判断が必要になりますので、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。